Printen プリンテン

プリンテンはドイツの西端にある街アーヘンAachenで継承されているスパイス菓子です。
現在のプリンテンは、小麦粉にスパイス、甜菜糖の粉末やシロップ、さらに膨張剤を加えて混ぜ合わせ、平らに伸ばした生地を長方形に切りそろえて焼き上げたシンプルな形のものがほとんどで、チョコレートコーティングを施し、アイシングやナッツなどで装飾したものも多く見られます。
スパイス菓子はドイツ各地で継承されていますが、アーヘンの『プリンテン』はニュルンベルクの『レープクーヘン』とならんで世界中にファンを持ち、クリスマス近くなると世界各地に向けて輸出される国際派。11月末 市庁舎前に街のシンボル『プリンテン坊や』が現れ、クリスマスに向けたカウントダウンが始まると、街はプリンテン一色に包まれて、ファンタスティックな世界が広がります。

中世から続く細い路地のあちこちに立つ専門店のショーウィンドウにはカラフルにデコレートされたプリンテンが並んび、店内から漂うスパイシーで甘い香りも相まって、おとぎの世界に迷い込んだかのよう。道ゆく人の歩みもゆっくりと楽しげです。
その起源はローマ軍…
アーヘンの街で愛され、深く根を下ろしているプリンテンですが、600年ほど前にやってきて、進化と変身をとげながら今の姿になった歴史をもっています。
古代ローマ時代の紀元前58年 カエサル率いるローマ軍がライン川流域まで遠征し、当時ガリアと呼ばれた一帯を属州としました。この時ライ麦粉に蜂蜜とチーズなどを加えて作った『プラセンタケーキ Placenta cake」が伝わり、ローマ軍が去った後もガリア各地で『麦粉と蜂蜜のケーキ』が作り継がれます。
クックドディナンの誕生

ガリアの地からローマが去って800年ほど経た12世紀 ベルギー ディナンの街のパン職人が麦粉と蜂蜜を合わせて作った生地を木彫りの型に押して焼くと、レリーフが浮き出て美しく、人気を博しました。
13世紀のフランドル(現在のベルギーとフランス北部にまたがる地方)ではローマ人が好んだ『プラセンタ』が由来とされる蜂蜜と麦粉を混ぜて作るケーキ菓子を『レーベンス・クーヘン』:「命のお菓子」と呼んで食べていました。そこに十字軍の兵士たちが遠征先のアラブから持ち帰ったスパイスが加えられ、14世紀にはフランドルを含むネーデルランド地域で、麦の粉に蜂蜜とスパイスを混ぜた生地を焼いて作る『Speculaasスペキュラス』が誕生しています。
ネーデルランド東部の街ディナンでは、この麦の粉に蜂蜜とスパイスを混ぜて焼くケーキを『クック ド ディナンCouque de Dinant』:「ディナンのケーキ」』と呼んで作り、名物になっていきます。
*ネーデルラント(Nederlanden)は、「低地の国々」を意味し、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクの3か国:ベネルクスにあたる地域
11世紀以降ディナンは銅製品の加工が盛んになり、その製品はクオリティーの高さとフォルムの美しさで人気を得ます。「真鍮製品はディナン製に限る」と評され、街は工業都市へと発展 それは現代 ヨーロッパで真ちゅう製の家庭用品や室内装飾品を指して『ディナン ドリー』と表現されることからも伺い知ることができるのです。
14世紀半ば 鋳造技術をかわれてディナンから隣国ドイツのアーヘンに移り住んだ銅職人がいました。彼は『クックドディナン』も携えてやってきました。
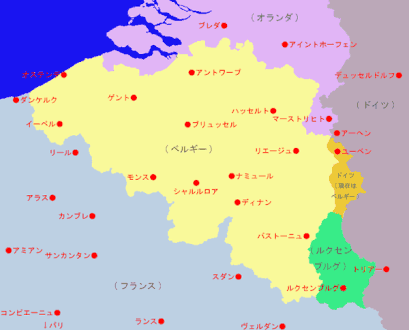
良質な温泉が湧き出るアーヘンは、水を意味する「Ahhaアーハ」から名付けられたとされ、紀元前3世紀からローマ人が好んで保養地として利用したのち、西暦800年に西ヨーロッパを統一したフランク王国のカール大帝(768-814)が都としたことで、カロリング朝ルネッサンスの舞台として文化が花開きます。そしてその後もカール大帝が建造した大聖堂で歴代神聖ローマ帝国皇帝の戴冠式が行われたことから、ドイツの歴史の中心的舞台として繁栄が続いていました。
↓(左)大聖堂(中)ドーム内モザイクの天井(右)戴冠式で使われた皇帝の玉座
『Printen プリンテン』誕生
ディナンの街から運ばれたクック・ド・ディナンにヒントを得て、アーヘンで デザインが彫り込まれた木型に麦の粉に蜂蜜とスパイスを混ぜた生地を押し入れて作るレリーフの浮き出た生地を焼き上げると、「印刷する」「焼き付ける」などの意味をもつフラマン語の「Prent」から『Printen プリ(レ)ンテン』と名付けられました。
当時スパイスは万病に効くとされ、薬局で販売される品でした。プリンテンも最初は薬局の棚に並べられ、修道院に併設された病院内で滋養食や薬として使われたり、修道士の保存食とされましたが、次第に市中に出てお祭の屋台を飾るようにもなっていきました。
彫り師によって作られた木型を使うことで、焼き上がりに浮かび上がるレリーフの装飾性は芸術の域にまで達します。蜂蜜とスパイスがたっぷり入った生地は保存性にも優れていましたから、食品としてのみならず、インテリアとしても人気を集め、プリンテンは全盛期を迎えます。
蜂蜜から砂糖へ
古来ヨーロッパの人たちが利用できる甘味料は蜂蜜に限られ、アラブの商人によってアジアから運ばれる砂糖(さとうきび糖:甘藷糖)は王族、貴族や教会関係者など一部特権階級の人しか口にできない貴重品でした。
カール大帝は領地内で養蜂を奨励し、税として蜂蜜や蜜蝋を納めさせています。そして王が亡くなると、そのお墓には蜂蜜を使ったお菓子のレシピが納められた…との伝説が語り継がれているところからもはちみつの貴少性を窺い知ることができるのですが、そんな甘味料事情が大きく変化したのは1700年代 イギリスの植民地政策により、カリブの島々や南米大陸で「さとうきび」の生産が広がると、ヨーロッパの国々にもさとうきび糖が大量に輸入され、 価格も徐々に下っていきます。アーヘンで作られるプリンテンにも「蜂蜜」に加えて「砂糖:さとうきび糖」が使われるようになります。 さらにアメリカ産の花蜂蜜も安価で輸入されるようになり、プリンテンの生産量はいよいよ増えていきました。
大陸封鎖令
1806年 ヨーロッパ大陸の国々の砂糖輸入に一大事がおこります。 同年ナポレオンは敵国イギリスと征服したヨーロッパの諸国との貿易を禁止する『大陸封鎖令』を発布 ヨーロッパ諸国はそれまでイギリスから入ってきていた砂糖や蜂蜜の入手が困難になってしまったのです。
甜菜糖の登場
窮地に陥ったかにみえたヨーロッパの甘味料事情ですが、タイムリーにも救世主が現れます。 1745年ドイツの化学者アンドレアス・マルクグラーフが、飼料用の甜菜(ビート または 砂糖だいこん)から砂糖を分離することに成功し、1802年には弟子のフランツ・アシャールが甜菜を原料とする製糖工場を建設 工業化が始まったのです。
これにより砂糖不足に困惑していたヨーロッパ各地で甜菜糖業が一気に広まりました。甜菜(砂糖だいこん)は飼料用作物として栽培していた地域もあり、冷涼な気候のヨーロッパでよく育ちましたから、この発明によりヨーロッパの国々は輸入さとうきび糖に依存することなく、砂糖を自給自足できるようになっていったのです。
甜菜の精製法により粉末のものとシロップが作られ、それぞれさまざまな味、色、風味、香りをもつ製品が製造され、流通し始めると、プリンテン職人たちは甜菜糖を使ってレシピに工夫を加え、新たな魅力をもったプリンテンが作り出されました。結果『大陸封鎖令』が解かれた後もアーヘンのプリンテンには甜菜糖が使われ続けることになったのです。
時を同じくして、19世紀に入ると、新たな膨張剤が生み出され、次々と工業化されていきます。『炭酸水素アンモニウム:鹿角塩』に続き、19世紀半ばには『重曹』が、19世紀末には『ベーキングパウダー』が発明工業化され、製パンや製菓の世界は変革の時を迎えました。
押し型から抜き型へ…
蜂蜜がさとうきび糖に代わり、さらに膨張剤が加えられるようになると、焼き上がりはふっくら柔らかくなり、味や風味、食感にも変化をもたらしましたが、図らずも精巧な彫りの美しいレリーフ浮き出させることを困難にしてしまいました。蜂蜜と麦粉のみから作られる生地は熱を加えても硬く締まって形が崩れにくいため、細かい文字や繊細なレリーフが彫り込まれたままの姿で焼きあがるのですが、膨張剤を使った生地はそうはいかなかったのです。

人々の嗜好はふんわり柔らかな生地を好むようになっていきました。木型を使って押し型をとる作業は大量生産には向きません。そんな事情も重なって木型を使用する作業スタイルは次第に姿を消し、1800年代には生地を広く伸ばして、抜き型を使って型抜きして焼くスタイルが主流になっていきました。
命名『アーヘナー プリンテン』
1820年頃 木型で型押しして仕上げるスタイルが姿を消しつつある中で、アーヘンのスパイス菓子は『Aschener Printen アーヘナー プリンテン 』の名称を与えられて街を代表する銘菓となりました。
レリーフ模様を失い、プレーンな四角形の姿になったプリンテンですが、チョコレートコーティングや、アイシンングで模様を付け、アザランやチョコチップさらにナッツやドライフルーツをトッピング、砂糖がけして白く仕上げるものも…と、バリエーションも豊富に華やかさを身につけて変身をとげていますので、ご覧ください。
プリンテン レシピ
専門店では1年中販売されているプリンテンですが、クリスマス前に各家庭で受け継がれるレシピでたくさん焼いて友人や親族にもおすそ分けして愉しむ文化は昔のまま。
ホームメイドのレシピは、小麦粉、スパイス、鹿角塩(PottascheまたはHirschhorn-saiz )甜菜シロップが使われるのが一般的。スパイスは シナモン、アニス、クローブ、カルダモン、コリアンダー、オールスパイス、ジンジャー等が選ばれます。
* 鹿角塩は工業化される以前もドイツでは修道院などでお菓子作りの膨張剤として使われており、焼く前の生地に独特の苦味を与え、わずかにアンモニア臭も残ります。「その苦味や香りも含めてクリスマス菓子の味!」と、プリンテンには鹿角塩を使うこだわり派も多数健在です。
それに対し、基本の材料は変えず、各々個性を出すのが専門店
フランツ通り91番地で1912 年以来4世代に渡って伝統のプリンテンを作り続ける家族経営の老舗『Printenbäckerei Klein Die Printenbäcker 』で取材させていただいたこだわりの材料とレシピをご紹介しましょう。
『プリンテン 』生地の材料は時計回りに…

Zucker-sirup(ツッカー-ズィールップ)= 甜菜糖シロップ
Zimt (ツィムト) = シナモン
Farin-zucker(ファリン-ツッカー)= 甜菜(サトウダイコン)から作られる粗製糖
Nelken(ネルケ) = クローブ
Koriander (コリアンダー)=コリアンダー
Anis(アニス)= アニス
Kandie - sucker (カンディス-ツッカー)=糖液を褐色になるまで加熱して作る キャラメル風味の氷砂糖
Weizenmehl(ヴァイツェンメール)= 小麦粉
作り方は
上記の材料に膨張剤としてNatron(ナトロン)= 重曹を加え、よく混ぜ合わせた生地を3日間おいて熟成させた後、 薄く伸ばし、型作って、焼き上げます。
*「3種類の甜菜糖(シロップ、粉末、顆粒)を使うのは、風味を豊かにするための工夫」とのこと 種類豊富で味も香りも風味も多彩なドイツのお砂糖を使いこなすのがプロのこだわり。
カール大帝とアーヘン
カール大帝はヨーロッパをはじめて統一した偉大な王として、トランプのハートに描かれている方。孫たちがその領土を3分割して建国したのが現代のイタリア、フランス、ドイツの原形となっているのですから、まさしく『現代ヨーロッパの父』と呼べる王さまです。
786年 カール大帝が宮廷教会として建設を始めた大聖堂は8角形のドーム形で、熱心なキリスト教徒であった大帝が、その形はキリスト教において「復活」を意味する数字『8』を重視したためと伝わります。814年にカール大帝が没するとその亡骸は堂内に埋葬され、以後永きに渡り多くの巡礼者を集めてきました。
長年歴史の舞台であり続けた教会内部は荘厳な空気が漂い、モザイク仕上げの壁面は、息をのむほどの美しさです…
8角ドームの教会は増築により1000年をかけて装いを整え、さまざまな建築様式の要素が融合した傑作として1978年に誕生した『ユネスコ世界遺産』では世界初12件のうちの1つとして認定されています。
大聖堂西側に位置する宝物館では、入るとすぐ出迎えてくれる黄金に輝くカール大帝の胸像(1349年作)に目を見張り、比類の無い美術工芸品たちに息をのみ、酔いしれることができます。
宝石がちりばれられた黄金のロータルの十字架(14世紀) 大帝の右手の骨を納めた聖遺物入れ… 研磨などないまま使われている大きな宝石たちに時代のゆとりを感じながら、カール大帝あってのアーヘンの街 アーヘンの街あってのプリンテン…歴史が作り上げた甘くスパイシーな伝統菓子プリンテンはこれからもアーヘンの街のシンボル菓子として大切にされていくに違いないと確信したのでした。

























